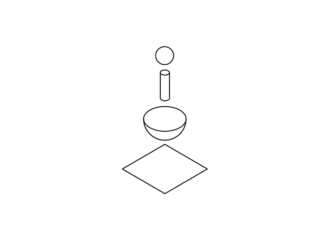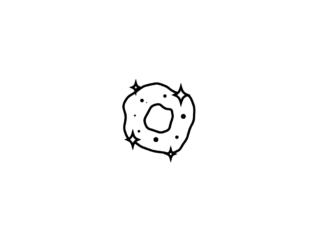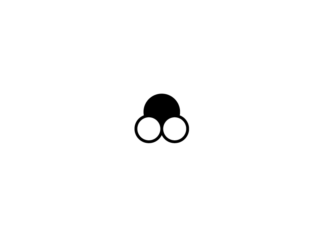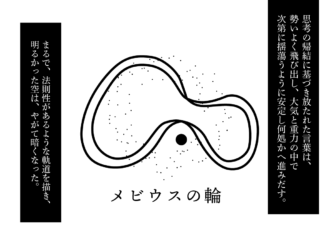音を立てながら勢いよく割れた。
飛び散った破片は飛び散りこちらに向かってきて、
体に打ち付けじゃらじゃら音を立て地に落ちた。
その欠片の上に膝をつき、
映し出される自分の表情は余所見に
その欠片の幾つかを拾い上げ、
忘れてなるものか、と
自分だけの箱にしまっておいた。
肌身離さず持っておいた大事な箱と共に、
あちらこちらを駆け回った。
時が長らく経つと、その存在すらを
すっかり忘れ、突如思い出したように、
奥底に仕舞われた箱を引っ張り出して
開けたところ、
埃を立てながら、
あの時の欠片たちは、
当然だが静かに眠っていた。
その欠片を手に取ってみたところ、
あの頃の鋭い角は箱に打ち付けられたためか、
角が取れており、あの時の透明感は失われ、
沈んだような質感になっているが、
何やら美しみを覚え、
どういうわけか懐かしさを見、くすりと笑ってしまう。
欠片に映る自分の顔とは、あの時から当然だが年を経ていた。
そうか、きっと忘れてなかった。
どうでもよいことだったのだ。
長らく誰にも見られることもなく、忘れられつつも、
僕の箱の中で、時間をかけながら、
ただ静かに、僕の輪郭を作っていた。
忘れるほどに、僕の中に馴染み息づいていたのだ。