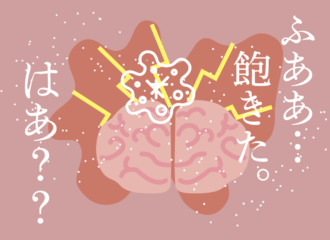時間を忘れてしまうくらいに、
どろどろになって労働に勤しんでいた。
くたくたになっていたのだろう。
気にもしない小石に躓いて転んでしまった。
躓いてしまったことにびっくりした瞬間に
忘れていた感覚を一瞬にして思い出し、
体がどっと重たくなってあらゆる神経が思い出したように痙攣する。
汗はきっと、とうに渇いていたのだろう。
水を補給するために、体を引きずるように井戸へ向かった。
水の跳ねる幻聴が、水が躍る幻覚が喉をごくりとうねらせる。
あの冷たい井戸水を喉に通せば、さぞ美味いに違いない。
ぼやけた視界に石造りの井戸が上下する。
骨を伝って自分の息づかいが聞こえる。
内心…僅かだが、井戸水が枯れていることを期待した。
枯れてさえいれば、ここで野垂れ死ぬことができるからだ。
そうすれば、全て終わることができるからだ。
そうであれば、こうなる運命であることを悟り、諦めるも何も受け入れざるをえないからだ。
だから、こうして毎日、僅かな期待を胸にこの穴に戻ってくるのだ。
石垣の碁盤目が大きくなって大きな四角形が見えたならば、もうひと踏ん張りだ。
枠をぐっと掴み最後の力を振り絞って立ち上がる。
ぐっと目を瞑り真っ暗になった眼を開けると、そこにはやはり水が湧き出ている。
そしてその水は体の隅々までに行き渡り生き返らせるのだ。
生き返らせをしたものの、残念な気持ちを錘に井戸にもたれ掛かって見上げる空には、無邪気に煌びやかに輝く星空が広がっているのだ。